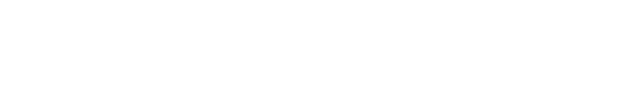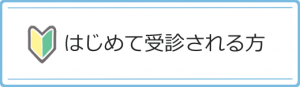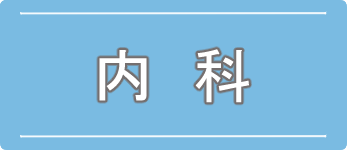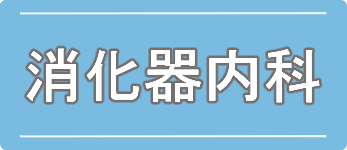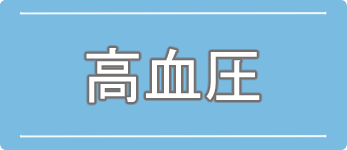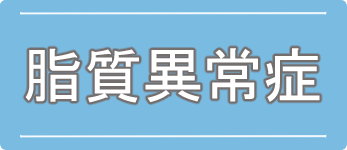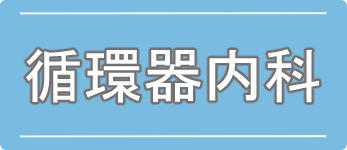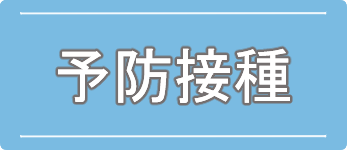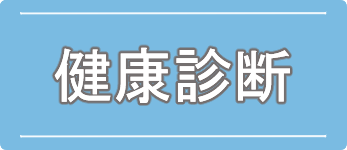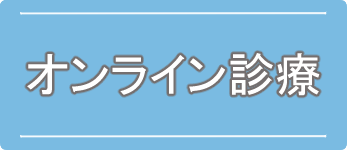高血圧
高血圧はなぜ治療が必要?
「高血圧」という病気は、中高年の方にとって最も身近な病気の一つかもしれません。
平成28年に行われた厚生労働省の調査によれば、40歳以上の人のおおよそ半数が高血圧にかかっているといわれています。
日本には約4300万人の高血圧患者がいると考えられていますが、実際に医療機関に通院している患者数は全国で約2500万人しかいません。
つまり、約1800万人もの人たちが高血圧であるにも関わらず適切な治療を受けていない計算になります。
高血圧はほとんど症状がないため、病院を受診せずに放置してしまう方が多いということです。
では、高血圧を放置すると何がいけないのでしょうか。
高血圧を放置していると、心臓病や脳卒中およびそれらによる要介護状態 (麻痺、寝たきりなど) や、腎不全 (透析) 、認知症といった病気を引き起こす危険性が高まります (後述)。最悪の場合、急性大動脈解離による突然死を引き起こすこともあります。
そのため、高血圧は別名 "サイレントキラー" (沈黙の殺し屋) とよばれています。
厚生労働省 HP より引用 (https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai23/dl/gaikyouR5.pdf)
上の図で灰色の実線は、脳血管疾患による死亡率の推移を表しています。
日本人は古来より塩分摂取量が多い国民で、日本人の死因第一位は、1981年に悪性腫瘍に抜かれるまで、長らく「脳血管疾患」でした。
そして脳血管疾患による死亡率が最も高かった1960年代の平均寿命は男性 67.7歳、女性 72.9歳と、今よりも10年以上短かったのです。
脳卒中による死亡率が低下したのは、高血圧治療が広まったことが理由の一つと考えられています。
当院の高血圧治療
当院では、高血圧の診断や原因を調べるための検査を行うとともに、飲み薬による治療も行っています。当院では初診時に尿検査と心電図検査を行います。
高血圧は心臓病につながる病気です。心臓や血管は一度傷めてしまうと二度ともとの健康な状態には戻りません。
高血圧の治療は、一般の内科や外科ではなく循環器内科を受診することをおすすめします。
当院では「ただ顔を見るだけで薬を出して終わり」「必要な検査をせず漫然と長期処方」のような診察ではなく、聴診器を用いた丁寧な身体診察を基本とし、心電図・心臓超音波検査で心臓をきちんと評価したうえで一人ひとりに合わせた治療薬を選択し、心臓病を防ぐために血圧をしっかりと治療するよう心がけています。
高血圧は当院が最も力を入れている疾患の一つです。
症状のない早期の段階から高血圧をしっかりと治療し、将来の心臓病・脳卒中を未然に防ぎましょう。
予約不要で気軽に受診できます
健診で血圧が高いといわれた方、高血圧が心配な方、転勤で広島にやってきて新たにかかりつけ医をお探しの方、以前病院に通っていたけど忙しくて通院が途絶えてしまった方、どなたもご相談ください。
高血圧の治療を通して、働く世代の方々をはじめ、地域のみなさまの健康をサポートするお手伝いができれば幸いです。
予約不要で受診できますのでお気軽にご相談ください。
※Our apologies but we are unable to offer you any assistance in English. If you want to get a medical examination in English, please go to another hospital.
目次
そもそも血圧とは?
血液は心臓から出て、体中の血管を通り、再び心臓に戻ります。
このとき、血液が血管の中で壁に押し付ける力を「血圧」と呼びます。
心臓が収縮したときの血圧を収縮期血圧(上の血圧)、拡張したときの血圧を拡張期血圧(下の血圧)といいます。
病院で測った血圧が140/90mmHg以上、ご自宅で測った血圧が135/85mmHg以上で高血圧と診断します。
血圧が高くなってしまう一番の原因は塩分のとりすぎです。
なぜ塩分をとりすぎると血圧が高くなってしまうのか、その理由を下に記載しました。
専門的で難しい内容のため、読み飛ばしていただいてかまいません。詳しく知りたい方だけお読みください。
なぜ塩分をとりすぎると高血圧になってしまうのでしょうか。
その理由には、我々の祖先が海から陸上に上がってきたときから体に備わっているシステムが関わっています。
我々の祖先は、食塩摂取の困難な自然環境で生命を維持するために、貴重な塩分 (ナトリウム) を体に留め、適切な血圧を保つ機構 (レニン・アンジオテンシン系) を発達させました。
しかし飽食の現代において、食塩はむしろ過剰摂取となっています。ナトリウムは生命維持に必須の元素ですが、多すぎても体内の水分バランスを乱し神経障害などを生じます。そこで過剰な食塩摂取に対して、我々の体はレニン・アンジオテンシン系を抑制することで対応します。それでもなおナトリウム排泄が十分でないとき、体は血圧を高くして腎臓に負荷をかけて過剰なナトリウムを体外に排泄するのです。
また血圧は常に一定というわけではなく、季節や体調、状況によって変動します。診察室では通常、高めに測定されることが多いですが、人によってはご自宅での血圧の方が高いこともあります。
そのため、ご自宅でも血圧を定期的に測定することをおすすめします。
家庭血圧の測り方や家庭血圧計の選び方は下記リンクにて解説していますのでご参考にしてください。
高血圧の症状は?
高血圧とは、血液が心臓から出て、血管の中を流れているとき、血管の壁に負担がかかっている状態のことです。
この負担が続くと、血管の壁が硬くなります。この状態を「動脈硬化」と呼びます。
動脈硬化は最初は何も感じないことが多いです。そのため、多くの人が高血圧を気にせずにそのままにしてしまいます。
しかし、高い血圧が続くと、脳や心臓、腎臓にダメージを与えることがあります。すると、胸の痛みや呼吸困難、頭痛や吐き気、視力低下、あるいは意識を失うなどの症状が現れるおそれがあり、放置すると大変危険です。虚血性心疾患を発症すると、胸の痛みや息切れがみられます。特に、高度な高血圧(血圧が180/120mmHg以上)では、生命にかかわることがあります。
40~64歳で血圧120/80mmHg未満の人と比較して、心臓血管死のリスクは血圧140/90mmHg以上で2.99倍、血圧160/100mmHg以上で5.23倍、血圧180/110mmHg以上で8.50倍になります1)。
たとえ軽度の高血圧であってもその状態が長く続くと、気づかないうちに動脈硬化が進んでしまい、脳卒中や心臓病、腎不全 (透析) 、認知症、寝たきりのリスクが高まります。
脳や心臓・腎臓が一度ダメージを受けると、発症前の元の状態には回復できないことが多いです。
ですから、これらの病気を発症する前に、血圧を適切に治療しておくことがとても重要なのです。
当院では毎回の診察で聴診器を用いて心臓の雑音がないかを確認し、定期的な心電図検査や心雑音聴取時などには心エコー検査を行い、高血圧の合併症を早期に発見するよう心がけています。
1)Fujiyoshi A et al : Blood pressure categories and long-term risk of cardiovascular disease according to age group in Japanese men and women. Hypertens Res,35, 9,947-53, 2012
高血圧は認知症や日常生活動作低下のリスク
高血圧治療ガイドライン 2019 (日本高血圧学会) より引用
上の図は (A) 血圧別に見た将来の血管性認知症発症リスクおよび (B) ADL 低下 (=日常生活に必要な動作が自分で行えず、介助を要すること) のリスクを示しています。
(A) 血圧120/80mmHg未満の人と比べて、血管性認知症リスクは血圧140/90mmHg以上で5.9倍、血圧160/100mmHg以上で10.1倍になります。
(B) 同様にADL 低下リスクは血圧140/90mmHg以上で1.55倍、血圧160/100mmHg以上で2.96倍になります。
高血圧の原因・本態性高血圧と二次性高血圧
高血圧の原因として、医学的に特定の病気が原因となっている場合を二次性高血圧とよび、専門医療機関での検査・治療が必要です。
当院では二次性高血圧が疑われる患者さんに対して適宜検査を行っています。
しかし高血圧のうち、90%以上は特定の病気が隠れているわけではなく、いわゆる生活習慣病であり、食事 (塩分のとりすぎ) 、運動不足、肥満、体質 (遺伝) といったものが原因です。
BMIが20未満の人たちと比較して、BMIが25以上の人たちは、高血圧発症のリスクが1.5~2.5倍になることが知られています。
*BMI=体重 (kg)/身長 (m)の2乗
二次性高血圧をきたす代表的な疾患
腎血管性高血圧
腎臓に血液を送る血管である腎動脈が、動脈硬化などにより狭くなり起こる病気です。腹部の聴診で血管雑音が聞かれます。腹部超音波検査で腎動脈の狭窄を確認します。
原発性アルドステロン症
副腎とよばれる臓器から分泌されるアルドステロンというホルモンが過剰に分泌される病気です。アルドステロンは血圧を上昇させるとともに、カリウムという物質を尿中に排泄します。これにより四肢の脱力がみられることがあります。血液検査で低カリウム血症を認めるのが典型的とされますが、実際には認めないことも多いため、血液検査でアルドステロン・レニンを測定してスクリーニングします。
クッシング症候群
副腎から分泌されるコルチゾールというホルモンが過剰になることで起こる病気です。高血圧の他、糖尿病や脂質異常症、肥満、満月様顔貌などがみられます。診断には内分泌学的検査が必要となるため、疑われる場合は専門医療機関に紹介します。
褐色細胞腫
アドレナリンなどのカテコラミンが過剰産生される病気です。副腎や交感神経節に発生した腫瘍が原因となります。発作性の頭痛、動悸、発汗などの症状がみられます。血液検査でカテコラミンの上昇を確認します。腹部画像検査で腫瘍が見つかることもあります。治療の基本は手術で腫瘍を摘出することです。
先端巨大症
下垂体から分泌される成長ホルモンが過剰になることで起こる病気です。高血圧の他、糖尿病や脂質異常症、手足などの末端が肥大したり額や下顎が突出した顔貌がみられるようになります。靴や指輪が入らなくなったという患者さんもおられます。血液検査で成長ホルモンを測定します。治療は手術で下垂体腺腫を摘出することです。
甲状腺機能亢進症/低下症
甲状腺はのどぼとけの下にある蝶のような形をした臓器です。甲状腺ホルモンを分泌し、体の代謝を調節する役割を担っています。この甲状腺機能が過剰になったものを亢進症、低下したものを低下症とよびます。いずれの場合も血圧は上昇しますが、亢進症では収縮期血圧が高くなり、低下症では拡張期血圧が高くなります。治療は甲状腺の機能を適正レベルに調整することであり、飲み薬が基本となります。
高血圧の検査
●心電図検査
心電図検査は心臓の活動を電気的にチェックすることで、高血圧による心臓への影響を簡単に調べることができます。
動悸や胸痛など胸の症状がある方では、24時間心電図検査 (ホルター心電図) を行い、労作時 (日中活動時) や夜間早朝の心電図変化を調べます。
●心臓超音波検査 (心エコー検査)
心臓超音波検査 (心エコー検査) はゼリーを塗ってプローブとよばれる機械を押し当てる検査です。放射線被ばくや痛みのない安全な検査です。
心エコーでは、心臓の動きが悪くなっていないか・心臓の壁が厚くなっていないかをチェックします。
高血圧では、心臓の壁が厚くなります。心臓の壁は筋肉でできています。
血圧が高いと、心臓に高い圧がかかり心筋がボディビルのように分厚くなります。これを心肥大といい、進行すると心不全の原因となります。
ボディビルのように心筋が厚くなると聞くと、一見心臓が強くなったように感じる方もいるかもしれません。
しかし、心臓は通常の筋肉と違い、24時間365日休むことなく動き続けています。
高血圧が続くと心臓がスタミナ切れを起こしてしまい心不全になってしまうのです。
当院では予約不要ですぐに行うことができますので、お気軽にご相談ください。
●胸部レントゲン検査
高血圧を放置すると最終的に心機能が低下し、心不全となります。
心不全を発症していないかを確認するために、胸部レントゲン検査を行います。
●尿検査
高血圧では内臓に負担がかかりますが、特に高血圧による影響を受けやすい2大臓器が、心臓と腎臓です。
高血圧による負担が腎臓にかかると、尿蛋白がみられます。
尿検査は、腎臓の状態をチェックできるもっとも簡単な検査です。
高血圧の治療
下に生活習慣の改善指導を示しています。
まずは生活習慣改善のアドバイスを行い、生活習慣の改善に取り組んでも血圧が下がらないときに、飲み薬を開始します。
ただし早急に治療すべき状態の場合は、生活習慣の改善と同時にお薬による治療を開始することがあります。
薬による降圧治療で血圧を10/5mmHg下げると、合併症の発症リスクは脳卒中で30~40%、冠動脈疾患 (心筋梗塞や狭心症) で20%、心不全で40%、全死亡で10~15% 減少することが知られています2)。
2)日本高血圧学会発行:高血圧治療ガイドライン2019.日本高血圧学会HP.
高血圧治療ガイドライン 2019 (日本高血圧学会) より引用
塩分は1日6g未満
野菜、果物、魚の積極的な摂取
お酒を減らす(1日量でビール250~500mL以下、日本酒1/2~1合以下、焼酎1/4~1/2合弱、ウィスキー・ブランデーシングル1~2杯、ワイン1~2杯弱)
1日30分以上のウォーキング
上の図は生活習慣修正による降圧の程度を示したものです。減塩 (・野菜摂取)+運動+節酒に取り組むことで、10/7mmHg程度の降圧効果が得られます。
肥満の人は体重を減らす(BMI 25以下)
体重を1kg落とすと、1.1/0.9mmHg血圧が下がるため、10kg減量すれば11/9mmHg血圧が下がります3)。
これは血圧の薬1剤に匹敵する効果であり、肥満を合併した高血圧の人では、ダイエットに成功すれば血圧の薬を止められる可能性があります。
3)NeterJE,et al. Influence of weight reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertension. 42(5):878-84, 2003
禁煙
タバコは血圧を上昇させるだけでなく、脳心臓疾患の発症リスクを高めます。さらにがんや肺気腫のリスクも上げるため、高血圧の治療においてのみならず健康寿命のために禁煙することが大切です。
高血圧は何科を受診すればいい?
高血圧は心臓病に関係することから、特に循環器内科の受診をおすすめします。
当院は高血圧をはじめ、心臓に関係する疾患全般を診療しています。
予約不要で受診できますので、お気軽にご相談ください。
薬を飲み忘れてしまいました。どうすればいいですか?
高血圧の飲み薬は毎日決まった時間に飲むことが大切です。ですが飲み忘れはどんなに気をつけてもなくすことはできません。
飲み忘れたときの対応を下に示します。
飲み忘れたからといって、急にこわいこと (脳卒中や心不全などの合併症) が起こるわけではないので落ち着いて対応しましょう。
また、飲み忘れた場合に次の服用のタイミングで2回分をまとめて飲むことはしないでください。ふらつきなどの副作用が出てしまうおそれがあります。
1日1回のお薬
その日寝るまでの間に気がついたら飲んでください。その日に気づかなかった場合に、翌日に2回分をまとめて飲むことはしないでください。
1日2回のお薬
朝の分を飲み忘れた場合、1回目を昼から夕方の間に飲み、2回目を寝る前に飲んでください。夕の分を飲み忘れた場合、寝るまでの間に気がついたら飲んでください。
※本ページの内容を無断で転載・引用・改変することを禁じます。引用される場合は、①引用部分を「blockquoteタグ」で挟むこと②当院ホームページへのリンクを載せること③貴社のオリジナルコンテンツが主であり当院HPからの引用部分が従であること、の3条件を満たした場合のみ許諾します。無許可での転載・引用・改変はGoogleへ著作権侵害によるコピーコンテンツ削除の申し立てを行います。
関連ページ
西田敏行さんを襲った虚血性心疾患 (狭心症/心筋梗塞) とその原因となる動脈硬化について解説
「診療内容」のページに戻る